LOGIN
ログイン情報を入力し、
MY K-MIXへログインしてください。
パスワードを忘れた場合
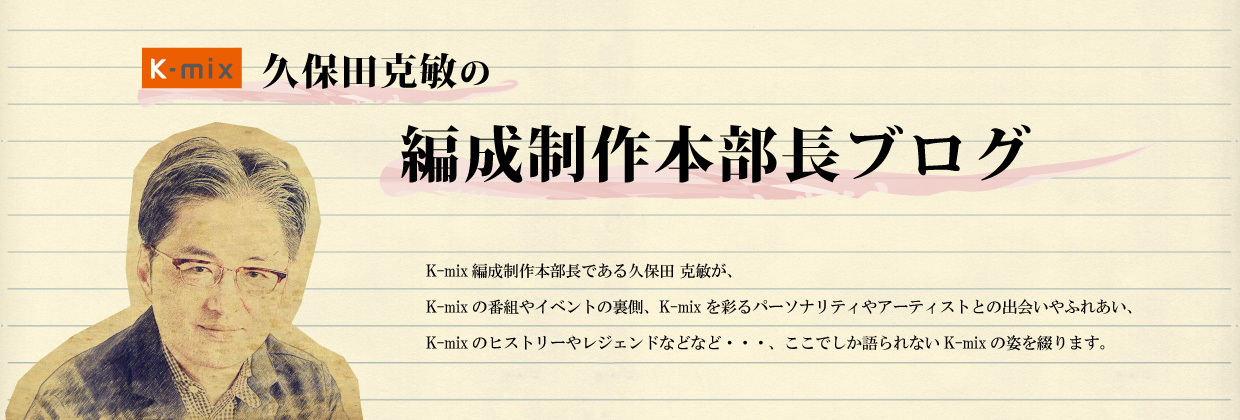
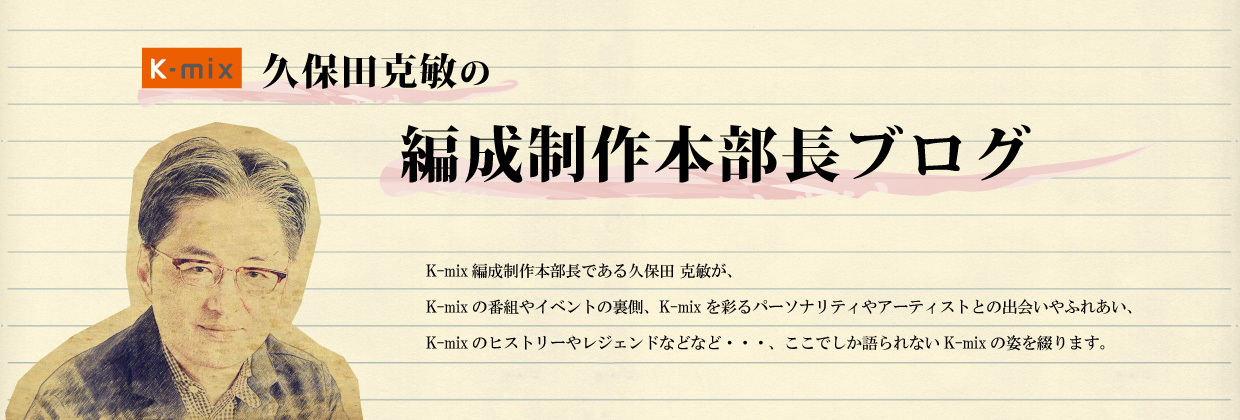
この仕事を長くしていれば、当然のように数え切れないほどのアーティストとの出会い、そして共同作業があります。今日はそんな中でも、もし将来、私の仕事録一覧を作って世間に公開するようなことがあったとしたら(実際、そのようなことをするつもりは全くありませんが)、多くの方々に興味を持ってもらえるであろう仕事、番組企画、そしてそれを成し遂げさせてくれたアーティストについてお話したいと思います。
いわゆる「ビッグ・アーティスト」と呼ばれる方々と、決して数は多くありませんが、お会いして比較的ゆっくりと時間をかけてお話しさせていただいた機会がいくつかありました。松任谷由実さん、山下達郎さんはその中でも代表的なアーティストですが、それにも増して、私が企画した番組に辛抱強く、しかも複数回に渡ってお付き合いいただいた方がいらっしゃいます。
小田和正さんです。
オフコース時代からメディアに対しては一定の距離を取っていて、テレビに登場することなどほとんどなかった小田さん。そんな小田さんがラジオ局キャンペーンを行うという話が舞い込んできたのは、1993年の晩秋、5枚目のソロ・アルバム『MY HOME TOWN』がリリースされた直後だったように記憶しています。普通、大物アーティストがラジオ・キャンペーンを行うといっても、それは東名阪福の大都市圏での話であって、静岡の、それもK-mix に来るなんていうことはまず考えられませんでした。しかし小田さんは浜松にやって来るというのです。
いくつかの伏線があったと思います。当時小田さんが所属していたレコード・メーカーのスタッフと、私を含むK-mix のスタッフが(他のメーカーと比較して)親交が深く、そして、特に当時小田さんのアーティスト担当であったM氏が、何故か私のことを面白がって、可愛がっていてくれたこと。どうもその辺りの事情が、小田さんの浜松行きを決めた要因だったのでは?と想像します。
しかし、このキャンペーンはある大きな約束事がありました。
普通、アーティストが、特にその方が大物であれば余計に、キャンペーンをすることになれば、まず第一に出演するのはその局を代表する生ワイド番組、というのが、局側もメーカー側も共通した認識でした。ところが小田さんは生放送には出演しない、というのです。その代わりにインタビューと楽曲オンエアで構成された長尺(最低でも60分)の録音番組を制作して、放送して欲しい、というのがメーカー側からのリクエストでした。
私は密かに「やった!」と心の中で呟いたことを今でも忘れません。
「ロング・インタビュー番組」というのはそのアーティストの思い、考えをじっくりと聞き出すものですが、それは単に「アーティストがしゃべりたいこと」を聞くためだけのものではなく、「このアーティストに何をしゃべらせたいのか?」という、聞き手=制作者の意図があって初めて成り立つものだと私は常々思っていました。それが「小田和正」という、これまで音声メディアに露出されることが少なかった超大物アーティスト相手に作れるということに、とても興奮していたように思います。
とは言っても、私はまだ30歳にも満たない番組ディレクターに過ぎません。小田さん相手に私がチャレンジしたいことを成し遂げるためには、そう、インタビュアー、それも私と同じベクトルを持っている、力のある聞き手が必要なのです。だからと言って、大物パーソナリティを雇うバジェットはないし、バジェットのあるなしに拘らず、この企画には巨大で険しい急勾配の山にアタックするような多少無謀な、そして、もし小田さんに返り討ちされても、すぐに立ち上がって私と一緒に再びアタックしていくような根性の座った若いパーソナリティ、もちろん、小田さんやオフコースに興味を持っている人間こそが適役だと思ったのでした。
私はこの31年間のラジオマン生活の中で、常に感謝の念に堪えないのですが、そうした私と同じベクトルと熱量を持つパーソナリティの人々に本当に恵まれてきたのです。「この人と一緒に高みを目指したい」と思う人々に・・・。
この時、私のパートナーとなってくれたのは、私の2期後輩の局アナ、江坂英香でした。彼女とはお昼の生ワイドを一緒に担当したり、まだ当時は言葉としてはそれほど市民権を得ていなかった「J-POP」について色々なアプローチで番組を作っていました。「とにかくしゃべっていないと落ち着かない」という“騒がしい女性”でしたが、彼女の音楽に対する感受性は鋭く、しかもそれを誰にでもわかり易い言葉で表現できることが、江坂英香という人の最大の武器でした。私の20代後半から30代初頭にかけてのキャリアの中で、彼女は必要な存在であり、実際に様々なことを一緒に成し遂げたと思っています。
更に彼女は「オフコース・チルドレン」だったのです!
60分の番組を作るにあたって、「事前に番組制作意図や進行フォーマットを作って送って欲しい。」とメーカー担当者から言われました。「小田さんの所属事務所に確認を取る必要があるから。」というのがその理由です。極めて当たり前のことなのですが、相手が相手だけに企画書作りは慎重にならざるを得ませんでした。
番組テーマは最新アルバム『MY HOME TOWN』の制作テーマに沿って、小田さんの「MY HOME TOWN」=横浜について聞く、という正攻法なものを考えていたのですが、そんな矢先、江坂から「どうしても小田さんに聞いて確かめたいことがある」と告白されました。それはオフコースの代表曲『Yes-No』に対する彼女が長らく抱えていたひとつの疑問でした。
江坂曰く「この曲は男性一人称で歌われているのではなく、『僕』と『君』との言葉のやり取りを詞にしているように私には思える。その解釈が正しいのか間違っているのかを本人に直に確認したい。」
確かに『MY HOME TOWN』に収録され、先行シングル『風の坂道』のカップリング曲は『Yes-No』のセルフ・カバー・バージョン(この時点ではアルバム未収録)で、『Yes-No』について小田さんに聞くのはあながち間違った選択肢ではないとも思いました。しかし、普通にこの曲の歌詞を眺めれば、男性一人称単数の歌と思うのが自然で、それを小田さんに聞いたところで「(君の解釈は)違う。」と一言で片付けられるのが目に見えていました。ということで一度は彼女にその思いを止まらせようと思ったのですが、江坂がオフコースの大ファンで、「こんなチャンスなど二度と来ないであろう。」と思い始めると、何とかそれを小田さんから聞き出してみたい(聞き出させてあげたい)、という気持ちに私は傾いたのです。そう、「こちらの聞きたいことを聞き出す。」というのが我々ふたりの、この番組を制作するにあたっての根幹にあったポリシーだったからです。
そこで江坂には「この質問は敢えて進行フォーマットには書かず、当日の打ち合わせでも話に出さず、収録途中に君のよいと思ったタイミングで小田さんにぶつけてくれ。」と話しました。江坂のその時のキラキラとした目は今でもよく覚えています。
さて、番組収録当日、小田さんはK-mix にやってきました。実は私は小田さんにお会いするのはこれが2回目でした。初めてお会いしたのはオフコースのファイナル・ツアーの浜松公演終了後の浜松市民会館(当時)の楽屋にお邪魔してご挨拶をさせていただいた時です。他のメンバーやスタッフが大きな楽屋で談笑したり、のどの渇きを潤しているのに、その時、小田さんは独り別の小さな楽屋で、セッティングされたキーボードに向かって、まるで思いついたメロディーを弾き試している、という雰囲気でした。レコード・メーカーのスタッフが私を小田さんに紹介した時も、チラッとこちらを見つめて「どうも・・・。」と一言返されるだけでした。正直に言えば、それは私にとてつもなく大きな緊張をもたらしました。それと同時に、オフコースがまさに終焉を迎えようとしていることを肌身で実感した瞬間でもありました。まるでザ・ビートルズの実録映画「レット・イット・ビー」を観た時に覚えたあの感覚と同じように・・・。
番組収録前の打ち合わせで、まず私と江坂は小田さんに番組の内容や進行、オンエアする楽曲の選曲について相談をしました。予めメーカーの担当者やマネージャーからどれだけの話がご本人に伝わっていたかは定かではありませんでしたが、小田さんは我々が説明している最中に、「君たちのやりたいように進めて、曲も君たちがかけたいと思う曲を選べばいい。任せる。」とおっしゃいました。でも、それは「面倒くさいから。」というのとは少し違ったニュアンスで私には伝わりました。私は念のためアーティスト担当のM氏やマネージャーのF氏に目配せしたのですが、「小田本人がそれでいいって言うんだったら、それでいいんじゃないの。」と言わんばかりの表情でした。
余談ですが、こういう姿勢は小田さんに限ったことではなく、本当のビッグ・アーティストに共通したもののように思います。ユーミン然り、達郎さん然りです。
それはまるで、私が大好きな20世紀を代表する巨匠指揮者のひとりで、人一倍ユーモアとアイロニーに溢れていたハンス・クナッパーツブッシュのある逸話を思い出させます。
ある時クナッパーツブッシュは、以前彼の演奏について否定的な記事を書いた若い新聞記者が取材に来た際、その時の無礼を詫びようとした彼にこう言い放ったのです。
なぁ、若いお人よ、大聖堂に向かって子犬が用を足したからといって、
大聖堂は微塵とも揺るがないのだよ。
「どんなことを聞かれようが書かれようが、簡単に自分の芸術の価値は変わることはない」という確信。真のビッグ・アーティストに共通する姿です。
インタビューは順調に進んでいきます。小田さんの話し方はどこか江戸の落語家のべらんめえ口調を想起させるもので、自分のことを「俺」と言い、私が持っていた小田さんのイメージは次々と覆されていきます。
自分のことを「俺」と言う小田さんですが、ご承知の通り小田さんの曲の歌詞に登場する男性一人称単数は『僕』です。多分、この収録の時だったと記憶しているのですが、この『僕』という一人称単数に話が及びました。その時の小田さんの言葉が今でもしっかりと私の心の中に残っています。
「俺だって本当は拓郎や陽水みたいに『俺』とか『あたい』とか使ってみたいけど、俺の声がそれを許さないんだよ。」
特にオフコース時代のアンチは、小田さんが書く詞とその歌声が「女々しい」という理由でそうだったのだと思います。まぁ、これは例えば『さよなら』という大ヒット曲から人々が勝手にイメージを膨らめてしまったこと、あるいはタモリさんが「オフコースのことが嫌いだ」とネタにしていたことなどに、大きな要因があったのだと思いますが、逆に私は小田さんほど自分の声に自覚的でそれを武器として、詞も含めどう表現したらよいか?ということを突き詰めて考えた人はいなかったのでは?と思っています。
閑話休題。
いよいよ、インタビューはその時を迎えました。
小田さんとの距離感が完全に縮まったと感じたであろう江坂が、その前の流れをぶった切るように、「今日、小田さんにどうしても聞いておきたいことがあるんです。」と小田さんに投げ掛けます。小田さんは「何だよ。」と答え、江坂は例の疑問をぶつけます。「『Yes-No』は男性一人称単数の歌ではなく、男女間の会話で成り立っている歌」説です。小田さんはそれを聞いて、歌詞を自分で呟いてみます。そして、江坂に何故そう思うのか?と尋ね、江坂の言い分に耳を傾け、しばらく思いを巡らせているようでした。そして、こう言ったのです。「君の気持ちはわからないわけではないけれど、やっぱりそれは「なし」だな。」と。
それを聞いた江坂はというと、涙を流し始め、「えぇ・・・。」とも「あぁ・・・。」ともつかない声を絞り出しました。おそらく、長年の疑問が解決したという終焉感と、自分の思いが小田さん本人によって否定されたことへのやるせなさの両方がない交ぜになって、溢れ出したのでしょう。そして、それを見た小田さんはというと急に動揺し、サブ(スタジオの機材がある側)の私やスタッフの方を向き、困惑とも苦笑とも取れる表情でこう嘆いたのです。「どうしろって言うんだよ。これは・・・。」それに対しM氏やF氏はお腹を抱えて大爆笑し始めました。曰く「小田がインタビューを受けて、こんなに慌てふためくことなんて初めてだ。最高に面白いものを見せてもらった。久保田君、ここはそのまま『生かし』でね」と。
こうして、小田和正というある種ベールに包まれていたアーティストの「素」の表情を捉えた番組「ALL ABOUT KAZUMASA ODA~MY HOME TOWN~」は出来上がり、放送されたのです。そして後日、私はM氏やF氏からこう提案されました。「また機会を見つけて、このロング・インタビュー企画は続けていこうよ。」と。その時の江坂と私の喜びと充実感は、筆舌に尽くし難いものがありました。
さらに少し経ってからのファンクラブの会報で、インタビューされることについて聞かれた小田さんは、印象に残っているインタビュアーとして江坂英香の名前を挙げ、逆に嫌いなインタビュアーとして、具体的な名前はもちろん出さないものの「最初から自分の頭の中に、俺や俺の曲についての結論みたいなものがあって、話をそっちへ持っていこうと躍起になっている人」とも語っていました(後日、小田さんやFマネージャーに聞いたところ、そのインタビュアーは私もよく知っている他局のアナウンサーでした)。
またこれも余談ですが、江坂英香の名前が小田さんファンの間で知られることになった結果、極限の妄想、嫉妬状態に陥った狂信的なひとりのファンが、江坂のあらぬ噂を記した怪文書を全国の放送局にFAXし、それを受け取った人から私宛に連絡がある、という今となっては笑える出来事もありました。
さて、実際にこの後4回程度、我々が東京に伺って、あるいは小田さんが浜松にいらしてインタビューは収録され、「ALL ABOUT KAZUMASA ODA」はシリーズ化されていきました。
中でも私が特に強く印象に残っている回がふたつあります。
ひとつは、オフコースや小田さんの作品のタイトルや詞に頻発する「ある単語」について、小田さんの思いを聞いてみたいと思ったことが発端になって作られた「ALL ABOUT KAZUMASA ODA~『風』~」です。例えば先ほども触れた『風の坂道』、そして何と言っても小田さん最大のヒット曲『ラブストーリーは突然に』のサビに登場する「やわらかく 君をつつむ あの風になる」などなど、小田さんの作品の中でとても印象的で、重要な意味を持つであろう「風」という単語に徹底的に拘った番組を作りたいと、私は思い立ったのです。
この企画の説明を私や江坂から聞いた小田さんは「君たち、なかなかいいところに目を付けたな。」とまず我々を褒めてくれました。その上で「こういう企画はラジオでもいいんだけど、映像作品として仕上げたらもっといい。」という言葉も忘れずに付け加えました。
ある狙いに焦点を定めたインタビューの場合、ただ相手に質問を投げかけるのではなく、事前に「この質問をしたら、こういう答えが返ってくるのでは?」という、こちらなりの「仮説」を立てて臨むことが重要だと、私は常々思っていました。「仮説」なので、それは覆されることもあります。それに執着しすぎると、小田さんから「勝手に結論付けるな!」と叱責されていたことでしょう。
この時も仮説を準備をしていたのですが、結果、小田さんが語り、江坂と私がまとめて結論づけたのは、小田さんが「風」という言葉を使う時、そこには大きくふたつの意味、使い方があるということでした。まずひとつは「時の移ろい」「時間の流れ」「過去・現在・未来という時間軸」を表現するための「風」、そしてもうひとつは「力」「支え」「希望」を表現するための「風」です。
もうひとつ、それはその後の「私の番組制作の在り方」や「リスナーへの向き合い方」という大きな命題に「普遍的信念」を抱くきっかけを与えてくれた回でした。
1996年2月1日、小田さんはオフコース時代の自身の楽曲をセルフ・カバーしたアルバム『LOOKING BACK』をリリースしました。先ほどの「Yes-No」のセルフ・カバー・バージョンもこのアルバムに収録されています。
このリリースを受けて、私と江坂は再び小田さんに立ち向かい、「ALL ABOUT KAZUMASA ODA~『LOOKING BACK』~」という番組を作ることになります。
この番組で我々が小田さんに投げ掛けた最大の問いはこのようなものでした。
「今回のアルバムのテーマは、その名の通り『LOOKIKG BACK』=「過去を振り返る」だとわかってはいるけれど、ただ振り返るだけならば、それをテーマに新曲を書いて、それらを収録すればいいのではないですか?何故、セルフ・カバーでなくてはいけないのですか?」
随分と生意気な物言いだと自分でもわかってはいます。でも、これくらいのことをしないと小田さんは本気にはなってくれないのです。
この問に対し、小田さんはこのようなことを語りました。
「俺のファンの多くは今、30代、40代の女性だ。10代や20代の頃、オフコースに熱中した彼女たちは、その後、恋をし、結婚をし、子供を産み、家庭中心の生活をするようになり、音楽に接して、気持ちを奮い立たせたり、慰めたりすることは自然になくなっていった。そんな中、育児や旦那の世話をすることが少しずつ減っていき、生活に余裕ができて、再び俺の音楽を聴こうと思いついたとしても、全く知らない新しい曲についていくことはなかなか難しい。だから、セルフ・カバーという形で、彼女たちが以前熱くなったり、心穏やかになった曲を再び取り上げ、今の小田和正が歌うとこうなるんだ、ということを聴かせることに大きな意味がある。」
「目から鱗」とはこのことです。私はこの小田さんの言葉を聞いてハッとしたことをはっきりと覚えています。
「聞き手の状況を理解し、要望、期待に応えながらも、決して安直な手段でクリエイトせず、自分も表現する。」
これはそれ以来私が番組制作の根底に必ず置く鉄則となりました。
また、この小田さんのアルバム制作がきっかけとなって、数多くのアーティストたちが、次々とセルフ・カバー・アルバムを作るようになったと思います。
随分と長くお話ししてしまいました。
最後に小さなエピソードをふたつだけ・・・。
オフコースがデビューしたのは1970年。レコード・メーカーは東芝音楽工業(後の東芝EMI)でした。その後、1984年にEMIの制作ディレクターであったN氏が新しく立ち上げたメーカー、ファンハウスにオフコースは移籍します。因みにこのN氏はEMI時代、オフコース以外にも、赤い鳥、RCサクセション、チューリップ、甲斐バンド、長渕剛、寺尾聰、稲垣潤一など、錚々たるニューミュージック&ロックのアーティストを担当し、ファンハウスを設立してからも、オフコース(小田和正)、稲垣潤一に加え、小林明子、岡村孝子、永井真理子、辛島美登里、シングライクトーキング、大事MANブラザーズバンド、ACCESS、斉藤和義、THE YELLOW MONKEYといったアーティストを輩出していった方です。
小田さんにとって、おそらくN氏は自分の活動に欠かすことのできない存在だったのではないか?と思います。それをはっきりと物語っている事実があります。
ファンハウスはその後、経営悪化に伴い別のレコード・メーカーに吸収合併され、さらにその会社も全世界的なメジャー・レコード・メーカーの企業統合の流れの中、最終的にはソニー・グループの一員となり、現在に至っています。したがって今現在、小田さんの作品はソニーからリリースされているわけですが、そのパッケージに書かれている製品番号をよく見ていただきたいのです。普通、ソニーのCDなどの品番は「S」で始まったりするのですが、小田さんのCD(シングル、アルバム問わず)は、1989年10月にリリースされたシングル『Little Tokyo』から、2018年5月にリリースされ、現時点での最新作品であるシングル『この道を/会いに行く/坂道を上って/小さな風景』に至るまで、品番がすべて「FH」で始まっているのです。そう、「FUN HOUSE」です。小田さんの思いがここに詰まっていると言えるでしょう。
本当に最後です。
実は小田さんと私にはある共通点があります。
横浜生まれの小田さんは、中学・高校の6年間を全国的にも有名な進学校、聖光学院で過ごします。聖光学院はカナダに本拠を置くカトリック系修道会によって経営されている学校法人ですが、私が6年間通っていたのは、その兄弟校である静岡聖光学院でした。
場所と時代は大きく異なりますが、実は小田さんが生徒時代に指導を受けていた修道士のD先生は、私が高校在学中に静岡聖光へと副校長として赴任していらっしゃり、私はD先生からいろいろなことを学ばせていただきました。そして、D先生は古い卒業アルバムを持ち出して私に見せ、「これが小田君、これが鈴木(康博)君」と言って、オフコースの原点となった学園祭でのステージに上がっていた頃のふたりの卒業写真を見せてくれたものです。
『LOOKING BACK』。
ただ過去を振り返るだけでなく、今を知り、未来を見つめる、この大切さを小田和正という人から私は教わりました。
蛇足ながら、私が小田さんの曲の中で一番好きなものは、『LOOKING BACK』でもセルフ・カバーされた、オフコースのラスト・オリジナル・アルバム『Still a long way to go』収録曲『昨日見た夢』です。
この曲のサビにはこんなフレーズが歌われます。
「君が季節で 君が風で 君が世界で 君が愛で」

79.2MHz
78.4MHz
86.6MHz
80.3MHz
85.9MHz
85.8MHz
80.5MHz
78.6MHz
81.6MHz
83.0MHz
県内のラジオ、過去1週間分無料。
プレミアム会員で全国配信。